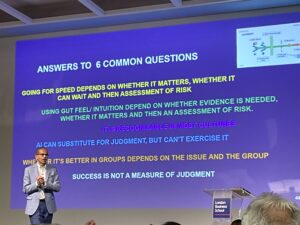Family Firm Institute (FFI) Global Conference参加のご報告(後編) 5期フェロー 内田博之
Author Profile
FBAAフェロー5期生
2024年5月まで、上場ファミリー企業において、買収、提携等の事業開発業務の責任者を務めると共に、一族の資産管理業務を担当
公認会計士・税理士、FFI Certificate in Family Wealth Advising資格保有者、日本証券アナリスト協会認定アナリスト
2024年5月まで、上場ファミリー企業において、買収、提携等の事業開発業務の責任者を務めると共に、一族の資産管理業務を担当
公認会計士・税理士、FFI Certificate in Family Wealth Advising資格保有者、日本証券アナリスト協会認定アナリスト